共有フォルダから考える2025年の崖とDX

2025年の崖とは?
ゴールデンウィークも終わり、2025年もあと2月足らずで半年が経過することになりました。「2025年の崖」は、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」の中に示されたもので、日本企業がレガシーシステムなどの課題を解決せず、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できなかった場合に、この2025年以降に大きな経済損失が生じるとされました。
あらゆる障害を乗り越えてこのDX推進を十分に行うのは至難の技であるとは思いますが、多くの企業においては、レガシーシステムの刷新や紙や手作業での業務をデジタル化推進によって効率化などの取り組みが見られます。
それら取り組みもあり、また2020年からの新型コロナウィルスによる感染拡大の影響して、DXが進められています。
「2025年の崖」は共有フォルダにも潜んでいる
それを放置した場合、情報資産の喪失や情報漏洩などがも起こるリスクも高まります。
共有フォルダで管理されている情報資産とはどのようなものか
構造化データと非構造化データ
共有フォルダで扱われるデータはこの内の非構造化データとなります。
それでは、この2つのデータの特徴を見ていきましょう。

構造化データ
構造化データは、データベースに格納されているような表形式のデータです。行と列の形式で表現されます。システムで管理しているデータで、「2025年の崖」の話題に当てはめるとレガシーシステムのデータは、構造化データとなります。
その特徴は、データの検索や集計がしやすい、SQL言語で命令ができるなどとなります。また、データがクレンジングされていることも多く、使いやすいものになっています。
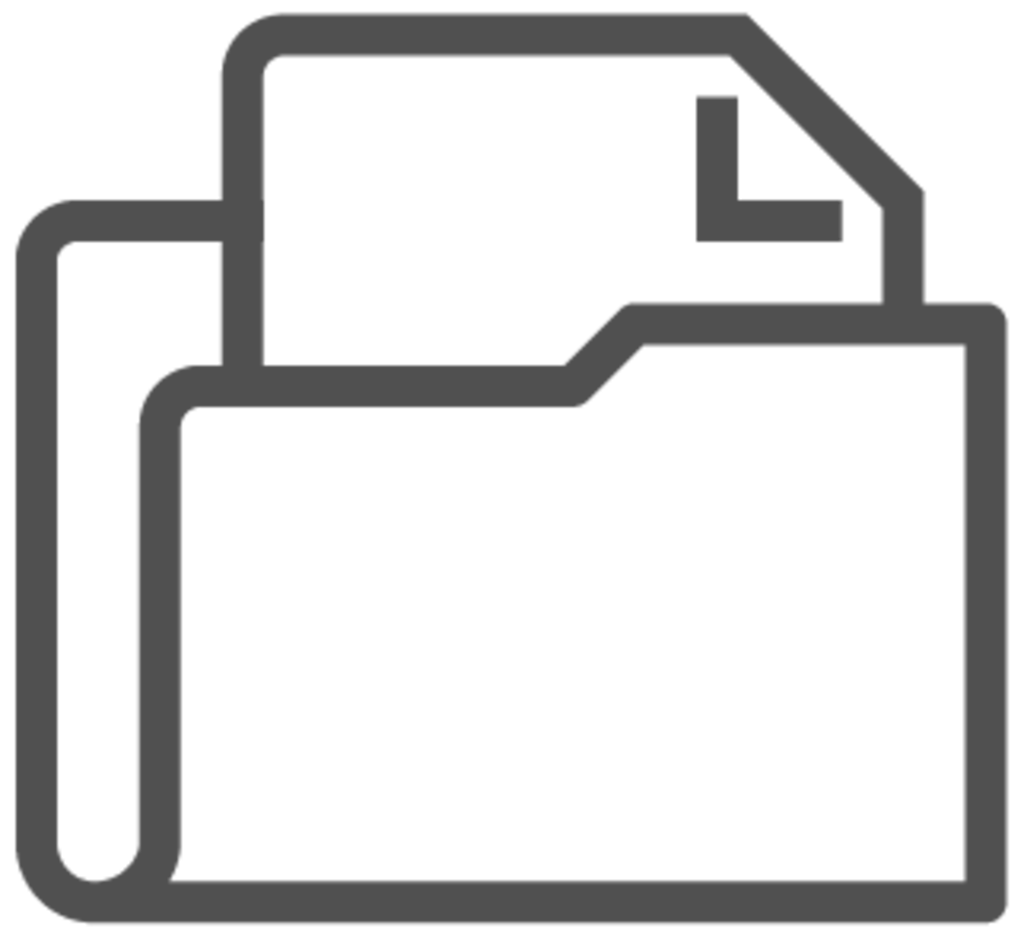
非構造化データ
非構造化データは、「構造化されていない」データで、officeソフトで作成したファイルやPDFファイル、画像ファイル、音声ファイル、動画ファイルなどとなります。
決まった形式を持たないデータで、そのデータ数は多く、場合によっては1ファイルあたりの容量が大きくなるものがあります。分析や集計にはそのまま使用できないため、OCR、自然言語処理、画像認識などの技術を介した加工が必要です。
非構造化データの課題
そんな非構造化データですが、多くの課題を抱えています。その課題を見ていきましょう。
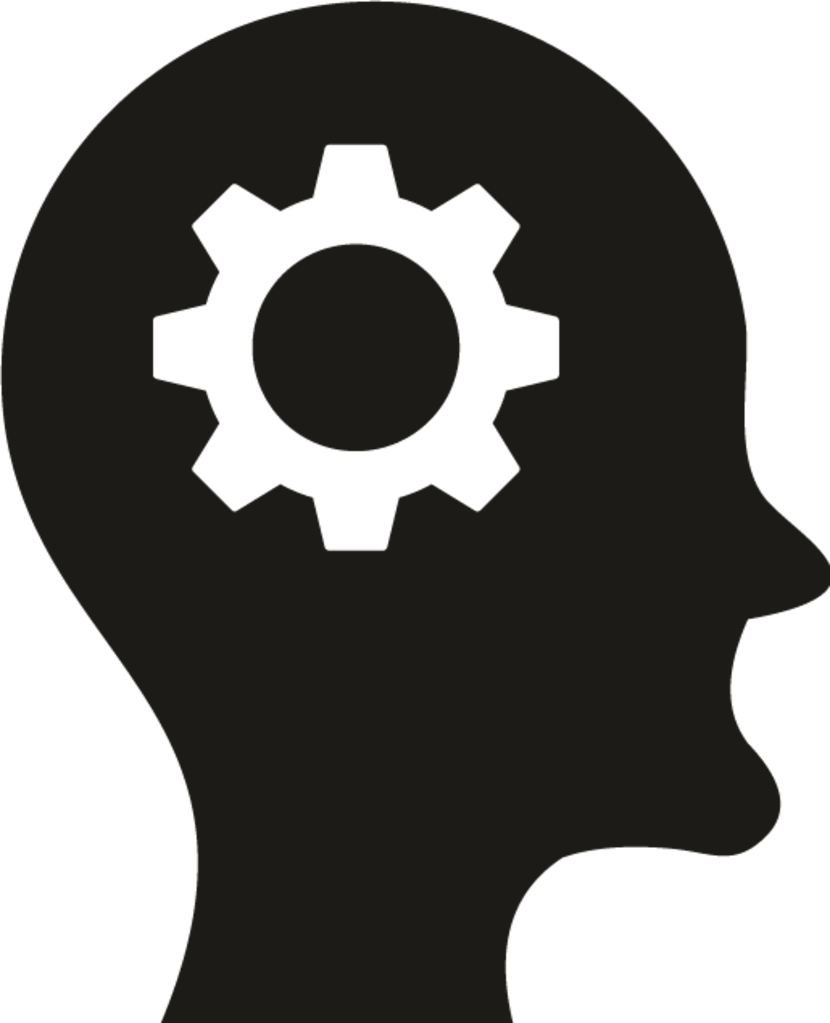
検索や分析に加工が必要
これは前述のとおりですが、非構造化データの形式は様々であるため、検索や集計がそのままではほぼ不可能です。このため、OCRや自然言語処理、画像認識などの技術でデータを加工する必要があります。
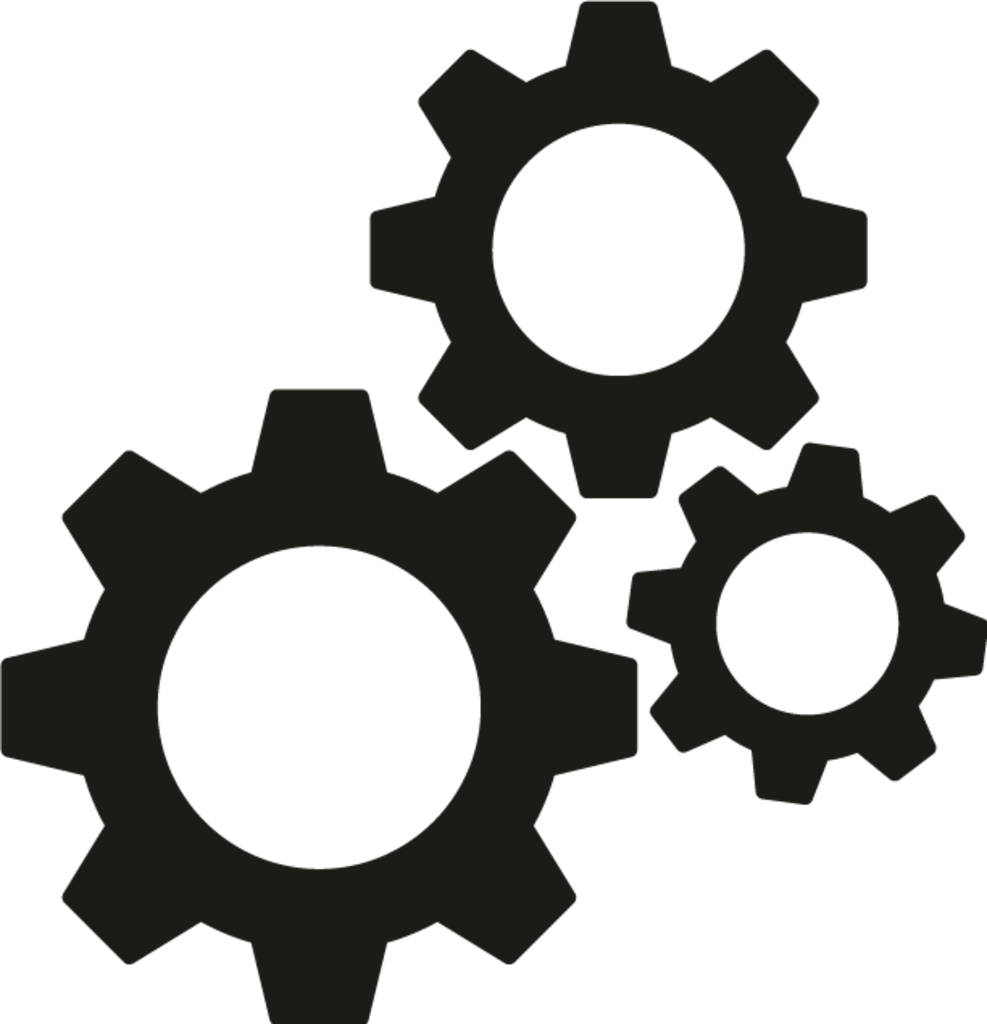
クレンジングが難しい
データに誤字や曖昧な表現などがあった場合、クレンジングを行うことによってデータの活用性が高まりますが、もともと使用されている言葉を変更してしまうと意味も損なわれる場合もあり、クレンジングを正確に行う難しさがあります。
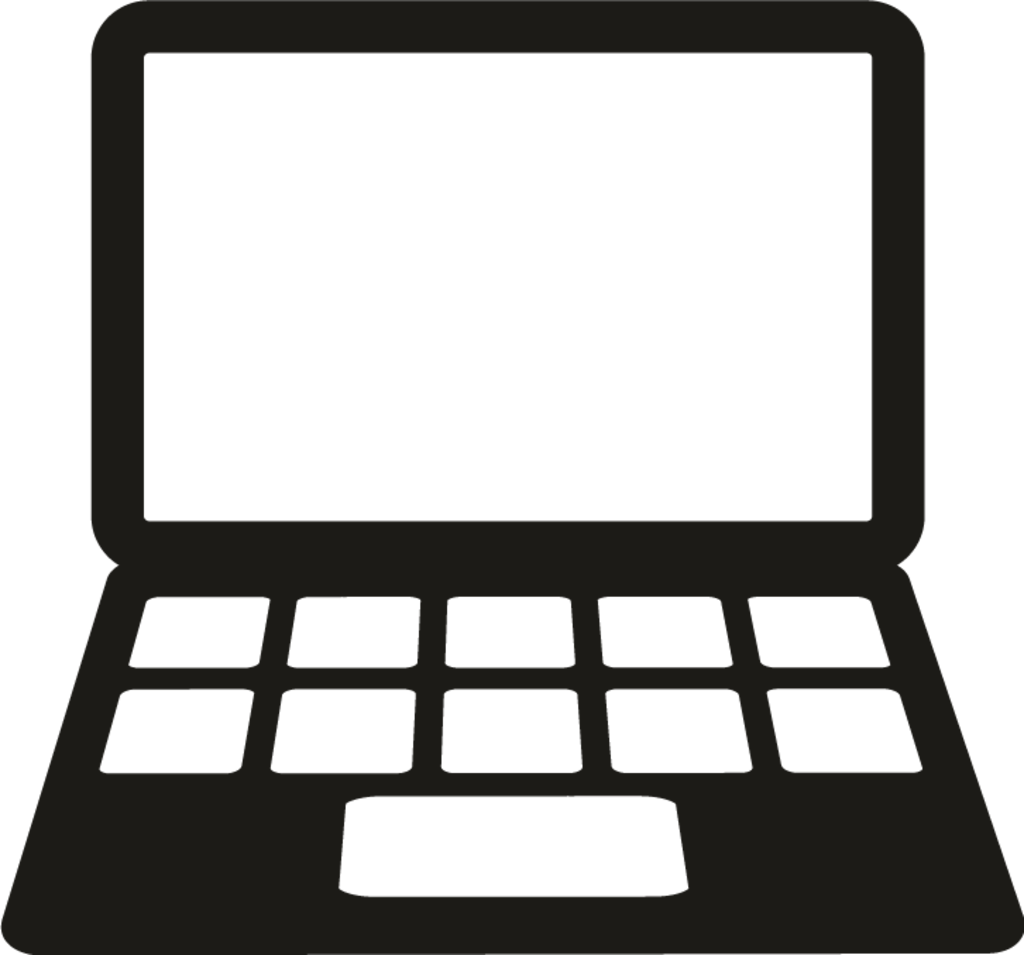
管理と保存のルールが必要
ファイルの数も多く、企業においては毎日たくさんのファイルが追加されていきますので、それらを管理する一定のルールを決めておかなければなりません。具体的には、データの保存年限の取り決めやアクセス権限、ファイルやフォルダのネーミングルールなどの組織の共通ルールが必要です。
また、セキュリティの観点からも情報漏洩のリスクも鑑みて、ルール化は重要となります。
「2025年の崖」に挑む共有フォルダの管理方法とは
このように「2025年の崖」に挑む際には、レガシーシステムの刷新だけではなく、情報資産の大きな割合を占める共有フォルダにも手を入れていくことが必要となります。
共有フォルダの課題をシステムの観点で解決する策としては、自社で管理しているファイルサーバーを高機能なクラウドドライブに移行するということがあげられます。これは、検索性のアップや社外からのアクセス、社外の組織との共有などがやりやすくなり、業務の改善などに効果があります。
しかしながら、文書管理の視点では機能性の高い保管システムを導入する前にルール化や不要なものなどの削減をすることをお勧めしています。
DXの推進に向けた対応策に共有フォルダ対策も含める
2018年の経済産業省が示したDXレポートでは「DXの推進に向けた対応策」は、以下のように示されています。
1.「見える化」指標、中立的な診断スキームの構築
2.「DX推進システムガイドライン」の策定
3.DX実現に向けたITシステム構築におけるコスト・リスク低減のための対応策
4.ユーザー企業・ベンダー企業間の新たな関係
5.DX人材の育成・確保
共有フォルダの見直しについてもこの手順に当てはめることができます。以下、順番に見ていきましょう。
1.現状調査ファイルの量(数や容量)、インタビューやアンケートでの定性情報の収集などを行います。
2.共有フォルダ利用のルールの策定
共有フォルダの管理方針(どのようなファイルを管理するのか、除外すべきものは何かなどの取り決め)、フォルダやファイルのネーミングルールなどを定めます。
3.棚卸しの実行
ルールを決めただけでは何も変わりません。ルール通りになるように棚卸しをして整理を行います。
4.教育
仕事をする上での当たり前のルールとして根付かせるために教育は欠かせません。また、新入社員に関しては、オリエンテーションなどで共有フォルダの管理の説明を受ける時間を作るようにします。
5.定期的な監査
ファイルは毎日増加し変化していきます。このため、1年に一度は棚卸しをする、また、監査によって状況の確認をおこないます。
このように全体のDX推進の中で共有フォルダについても、それぞれのフェーズに組み込むことをお勧めします。
また、最後の5は、「DXの推進に向けた対応策」にはないものとなりますが、共有フォルダのファイルは日々増加し変化していくものであるため、よい状態に保つために定期的な棚卸しや監査をお勧めしています。
共有フォルダの具体的な整理の方法やマニュアル作成については以下の記事を参考にしてください。
共有フォルダには、重要な情報資産が含まれています。 IT技術の発展やAI技術によって、非構造化データも活用が可能な時代になり、共有フォルダにある情報資産はこれからますます活用の価値のあるものとして注目されていくことでしょう。
※参考 経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~ https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
文書管理コンサルティング/石川
※関連記事
組織の知カラとは?
文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。
文書の業務効率化リスク低減を目指す
7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。
【必読】
文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。
このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。
文書管理ルール
ファイルサーバー共有フォルダ
ペーパーレス化支援
法定保存文書
文書管理研修サービス
維持管理支援
記事カテゴリ一覧
会社情報
© Nichimy Corporation All Rights Reserved.


