企業の電子文書管理を成功させるための必須要件と選択肢
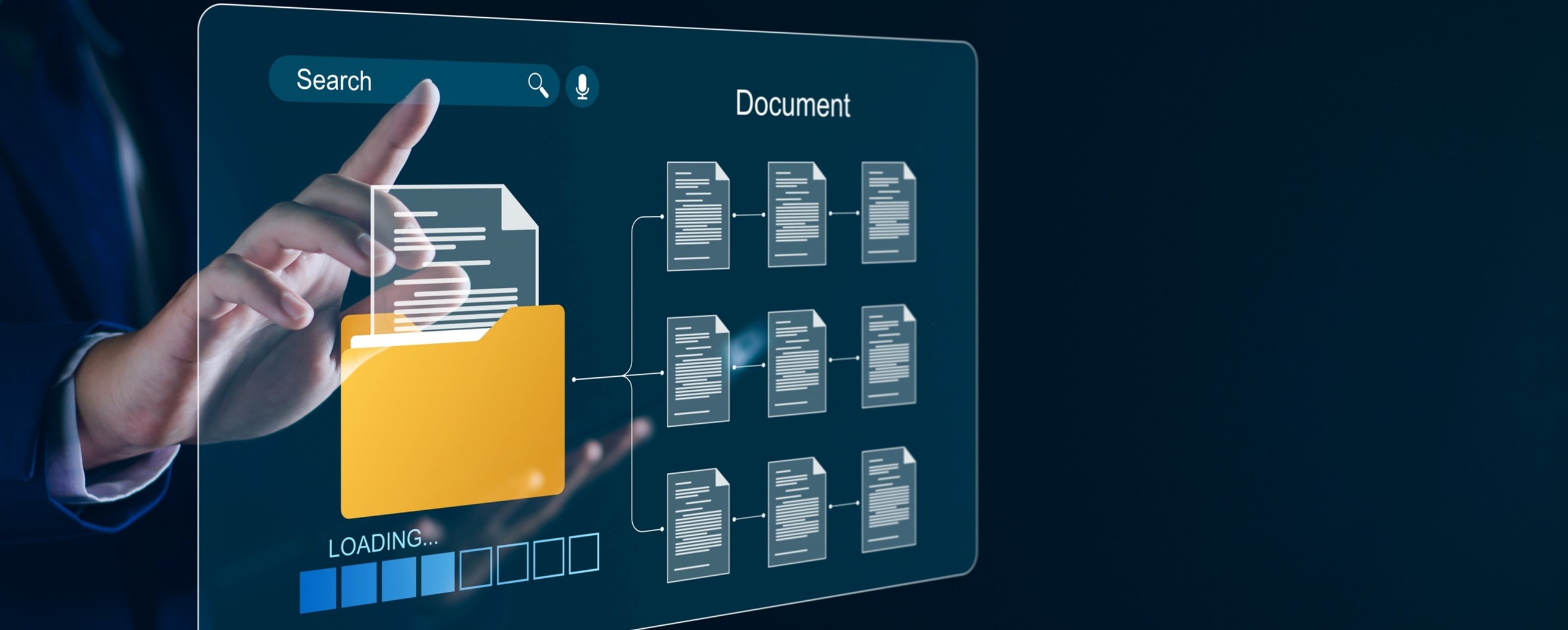
今回は電子文書の器として何を選択したらよいのか、そしてそれをどのような視点で検討するべきかを解説します。
文書管理システムと共有フォルダの棲み分け
電子文書の器として利用されているものには大きく2種類あります。1つは文書管理システム、もう一つはファイルサーバーやクラウドドライブといった共有フォルダになります。
まず、ここでは簡単に文書管理システムと共有フォルダの特徴を確認していきましょう。

文書管理システム
文書管理システムとは、企業や自治体などの組織が文書を効率的に保存、管理、検索するためのソフトウェアです。
■メリットデメリット
※メリット
・高度な検索機能で文書が探しやすくなり、業務効率がアップする。
・文書に対するアクセス権が詳細に付与でき、機密文書の管理がしやすくなる。
・版管理などで文書の取り間違いなどが発生しにくい。
・ワークフロー機能もあり、文書承認の足跡を残すことができる。
※デメリット
・検索性を高めるためには属性データを作成する必要がある。
・システム導入費用や維持費用が発生する。
■どんな文書を管理するか
重要文書・正式文書
検索性が求められる文書

共有フォルダ
対して、共有フォルダがどんな特徴を持っているのでしょうか。
社内でファイルサーバーを設置して利用したり、また、コロナ禍以降はクラウドドライブへ移行される企業もたくさんありました。
ただし、使い勝手としてはファイルサーバーからクラウドドライブになってもあまり変わらずツリー構造になったフォルダにファイルを格納していく方法で使われています。
■メリットデメリット
※メリット
・ファイルを格納するだけ。属性データを登録する必要はなく、簡単に使用できる。
・フォルダ構成を自由に設定できる。
※デメリット
・ルールがないとサイロ化しやすく、どこに何が入っているのかわからず探せなくなってしまう。
・ファイルやフォルダに対して属性データを入力することができず、検索性に乏しい。また、ツリー構造は物理的なフォルダ構造の1種類のみの利用となり、多観点での並べ替え表示ができない。
・クラウドシステムの場合、容量が増えると費用がかかる場合があり、それが足かせとなり自由度があまりない。
■どんな文書を管理するか
下書き文書、承認前の文書
以下の記事には、文書管理システムと共有フォルダのメリットとデメリットについて詳しく書かれています。
電子文書管理で必要とされる機能
次に電子文書を管理するにあたり、最低限必要とされる機能を確認していきたいと思います。
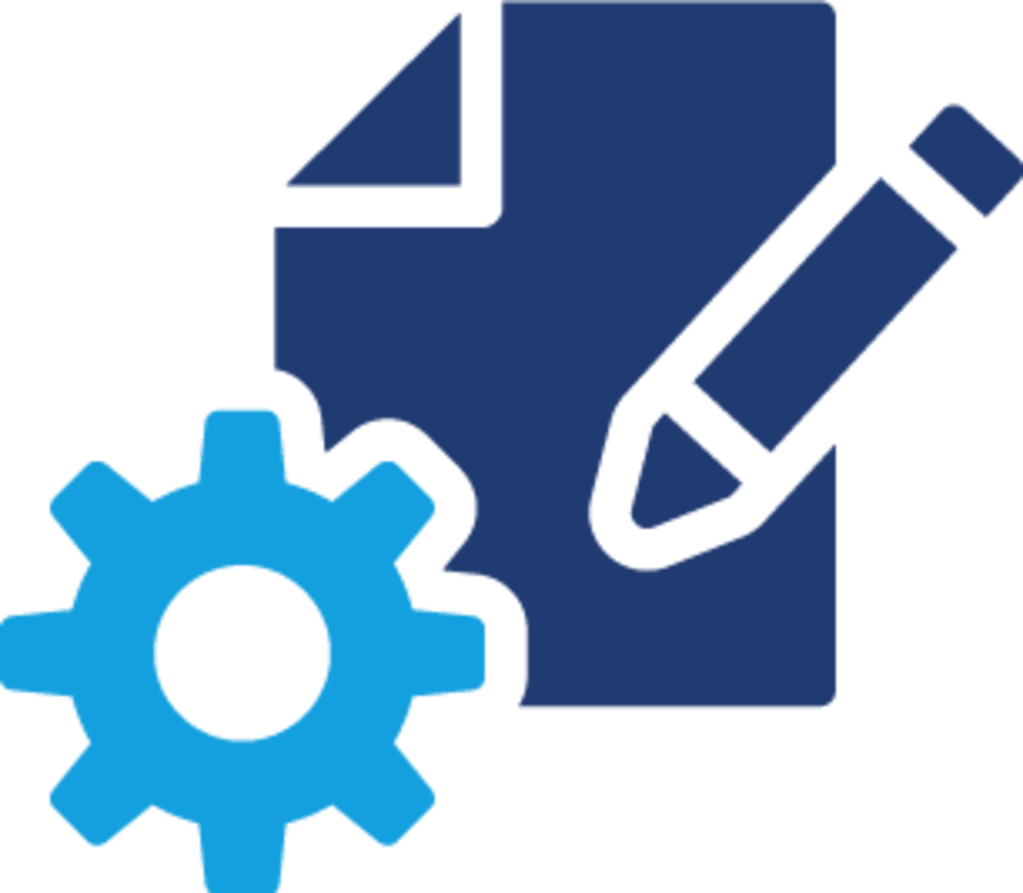
ライフサイクル管理
文書を一定期間保存して利用に供し、一定期間を終えたら正しく廃棄できるように管理します。特に法律で保存年限が決められているものもあるので注意が必要です。
このライフサイクル管理を行うためには、まずはどのような文書に対して何年の保存年限を定めるかをまとめた保存年限表の整備が必要になります。さらにその保存年限表に記載されている内容と文書ファイルを何等か紐付けておかなければなりません。
これには、文書管理システムであれば属性データの付与をしたり、共有フォルダであれば保存年限表の分類に合わせてフォルダ分けをしたり、年度ごとにフォルダを分けておくことで年限表から実際のファイルの場所にたどり着くことができます。

機密文書管理
機密レベルを定め、そのレベルに応じたアクセス権を付与する必要があります。ファイルそのものに対しても、組織で決められているセキュリティポリシーを満たす必要があります。
例えば、個別のファイルに対してパスワードを付与することを定めている企業もあります。

検索性を高める(属性データによる管理)
電子文書であれば、その内容をターゲットにして検索できる全文検索に対応できます。しかし、全文検索は可能性のあるものを大量に引っ張り出すことができるのは得意でも、特定するのは不得意です。
そのため、絞り込み検索ができるように整えておくことが必要になりますが、文書に対して属性データを付与しなければなりません。
例えば契約書の場合、よく使用される属性データには以下のものがあります。
・契約相手先
・契約年月日
・契約期間
・有効期限
・契約の種類
・金額
・自動更新の有無
全文検索でもヒットできるかもしれませんが、適合性は低くヒットしたものを後から選別しなければなりません。そうするとこのように予め属性データを作成しておいた方が使い勝手はいいことになります。
このように電子文書に必要な要件を見てきましたが、文書管理システムを導入すれば、これらの要件を満たすことができます。ただし、作成した全ての電子文書を文書管理システムに投入し、属性データを入力することは不可能です。
多くの企業では、管理が必要な文書、重要な文書は文書管理システムに投入し、そのほかの文書は共有フォルダに格納して管理しているようです。
とはいえ、中間に存在する文書や共有フォルダに格納された文書の管理は、かなり難航している側面も見られます。
毎日大量に生産される電子文書をもっと簡単に整理し、安全に利活用できることが理想です。
公文書管理委員会が検討している「新文書管理システム」では、保存期間表に関わる主な機能として、
「新文書管理システム内で作成する保存期間表に登録されたメタデータ(書誌情報)を基に、
・検討中領域に保存するためのフォルダ(大・中・小分類)の自動生成
(当該フォルダ内に格納する行政文書ファイルにもメタデータが紐付け)」
とあり、フォルダ管理を文書管理システムに取り入れていくことを示唆しています。
■参考:新文書管理システムを見据えた保存期間表について(令和6年11月19日(火)第109回公文書管理委員会)
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2024/1119/shiryou4.pdf
また、高機能なクラウドストレージには、属性データを付与する機能があり、この機能を使用することによって、ライフサイクル管理やワークフローなど文書管理システムに近い機能を実現することができます。
重要な運用ルールの取り決め
このように文書管理システムやクラウドストレージの高機能化によって、今まで不可能だったことが可能となり、ますます業務は効率化され、共有フォルダの文書もうまく管理されていく方向にあります。
ただし、どんな器を使っても文書管理ルールの取り決めはそれ以前の段階で必要なことは変わりません。以下に、文書管理ルールの取り決めについて、ここでは運用に関わることと、文書毎に関わることに分けて説明します。

運用に関わること
・文書管理体制
全体責任者の文書管理統括責任者、また、各部署の文書管理責任者、実務を行う文書管理担当者を定めます。
・文書管理年間スケジュール
年間通した文書管理活動のスケジュールもたてて、体制で決めた役割分担にタスクをリンクさせます。

文書毎のルール
次は文書に関わるルールを取り決めます。
・タグやキーワードの統制
先ほど属性データを付与することは重要としましたが、各人が思いつくままに属性を付与しては、探せない問題が発生してしまいます。
例えば同義語などは何を使うか、表記の統一なども必要です。
だたし、システムによっては、表記のゆれなどをフォローしてくれるものもありますので、その仕様を確認して、決定していくと無駄がありません。
・リテンションスケジュールの確定
文書の保管や廃棄、アーカイブなどのリテンションスケジュールを分類毎、あるいは文書毎に決めておきます。
・保存年限表の整備
保存年限表が無ければ作成する必要があります。また、法令で定められた保存年限は、法令の変更によって変わってしまうことがありますので毎年見直しが必要です。
大切な資産である電子文書をより安全に利活用できるよう、それにマッチした選択の一助になれば幸いです。
また、文書管理ルールについては、以下のホワイトペーパーにまとめていますのでこちらも参考にしてみてください。
以下よりダウンロードが可能です。
文書管理コンサルティング/石川
※関連記事
組織の知カラとは?
文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。
文書の業務効率化リスク低減を目指す
7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。
【必読】
文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。
このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。
文書管理ルール
ファイルサーバー共有フォルダ
ペーパーレス化支援
法定保存文書
文書管理研修サービス
維持管理支援
記事カテゴリ一覧
会社情報
© Nichimy Corporation All Rights Reserved.


