共有フォルダと文書管理システムのメリットとデメリット

多くはファイルサーバーや、クラウドドライブであると思います。また、文書管理システムに登録している場合もあるでしょう。
今回は、多くの企業で文書の保管先として使用されている共有フォルダと、文書管理システムについて説明します。
共有フォルダと文書管理システム
社内で作成されたWordやExcelなどの電子ファイルの保存先として、よく使用されているのは「共有フォルダ」であると思います。社内でファイルサーバーを設置して利用したり、また、コロナ禍以降はクラウドドライブへ移行される企業もたくさんありました。
ただし、使い勝手としてはファイルサーバーからクラウドドライブになってもあまり変わらずツリー構造になったフォルダにファイルを格納していく方法で使われているかと思います。
一方でこの記事で示す「文書管理システム」は、文書情報のライフサイクル(発生、処理、保管・保存、廃棄)を管理するシステムです。その利用は企業によって、全社的に使用されている場合、一部の部署だけの利用、一部の文書だけの利用など様々ですが、どんな形であれ何かしら導入している状況が見られます。
文書の入れ物ととして一番使用されている共有フォルダ
共有フォルダは、業務や状況に合わせて誰もが自由にフォルダ構成を作成することができるため、使いやすいと言えます。しかしその反面、使用ルールがないと部署ごと個人ごとに管理の仕方がまちまちになり、無法地帯になってしまい、結果ファイルが見つけられない、重複ファイルがたくさんある、誰が管理しているのかわからないため捨てられないファイルが大量にあるなどの問題が発生します。
■共有フォルダではむずかしいこと

検索性に乏しい
属性検索ができないため、ファイルを探すのに苦労します。
ファイル名に属性をつけるという方法もありますが、3つくらいが限度で、それを超えるとファイル名が長くなり、使いにくくなってしまいます。
また、全文で検索できたとしても、ある程度範囲を絞り込まないと結果が多く出過ぎて、文書を特定するのに苦労します。
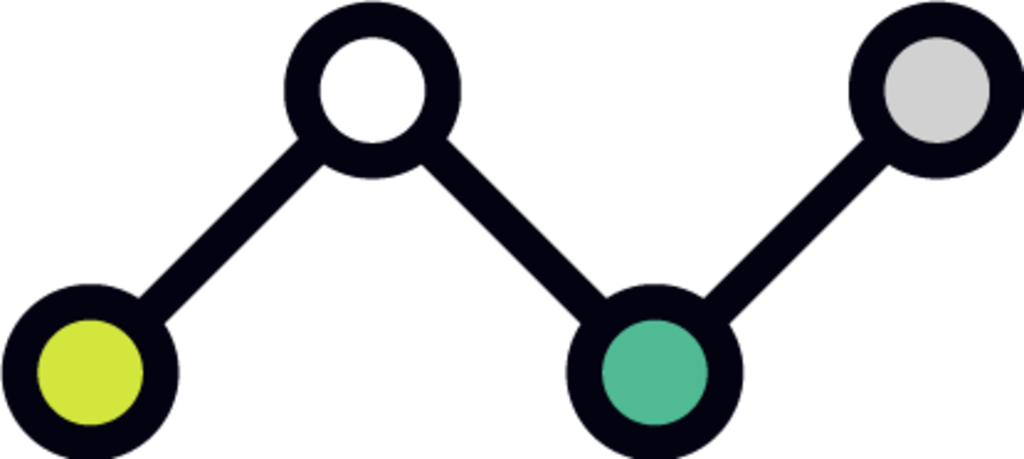
ツリー構造は、物理的なフォルダ構造の1種類のみ
フォルダ構造をどのようなするかは、共有フォルダの使い勝手に影響します。年度別→業務別で分けておくとライフサイクル管理がしやすく、また、業務別→年度別になっていれば業務を行う現場では便利です。
さらに、同じ部署でも年度別→業務別の方が利用しやすいと感じる人と、業務別→年度別あるいは他の構造の方が使用しやすいと感じる人もいます。
共有フォルダでは、このフォルダ構造をどうするか決める際に、決めかねてしまうことがあります。
文書管理システム導入のメリットとデメリット
前述したような共有フォルダでは出来ないことを、文書管理システムを導入することによって解決することができます。
それでは、文書管理システムの主な機能と導入のメリットデメリットを見ていきましょう。

文書管理システムの主な機能
多数のメーカーから文書管理システムが販売されており、それぞれ特徴を持っていますが、基本的な共通した機能を以下に紹介いたします。
・高度な検索機能
全文検索、属性検索、絞り込み検索などに対応し、共有フォルダよりもきめ細かな検索ができます。
・文書一覧とその並べ替え機能
物理的なフォルダ構造とは別の構造を表示することができるため、前述した、ライフサイクルを考慮した「年度別→業務別」も現場の業務にあった「業務別→年度別」でもそれ以外でも対応できるので、他のフォルダ構造の方が使いやすいのに我慢する必要はありません。
・リストの出力
文書一覧を印刷したり、ファイルにダウンロードしたりすることができ、データの2次利用が可能となってデータ分析を行ったり新しいものを生み出すことができます。
・通知機能
文書の保存期限、契約の満了などを通知し、廃棄漏れや契約更新漏れを防ぐことができます。
・承認・回覧
ワークフロー機能によって社内の承認の足跡が残すことができます。

文書管理システム導入のメリットとデメリット
上記のような機能を備えている文書管理システムですが、メリットをまとめますと以下のような点があげられます。
■メリット
・システムに接続できればどこからでも文書にアクセスできる
コロナ禍を経て、リモートワークも当たり前の働き方になってきました。リモートワークを円滑に行うには文書のアクセスが前提となりますが、文書管理システムで安全にリモートからアクセスが可能です。
・紙文書から電子文書に移行することにより、紙にかかるコストを削減できる
紙文書に必要とされるキャビネットやファリング容器、倉庫保管料などのコストが不要となります。
・文書を探す時間を短縮できる
高度な検索機能によって、文書が探しやすくなり、業務効率がアップします。
・アクセス権を詳細に設定できる
編集・閲覧のみなどの詳細なアクセス権により、情報漏洩のリスクが低減が図れます。
・文書を集中的に管理する
版管理機能などもあり、文書の取違いなども起こりにくくなっています。
また、文書管理システム導入にもデメリットがあります。
■デメリット
・導入コスト・運用コスト
オンプレミスではハードウェアやソフトウェアの導入費用、クラウドシステムの場合は運用コストがかかります。
・データ作成費用
文書管理システムで運用したい文書が紙文書である場合には電子化コストが必要になります。また、電子文書の場合は電子化費用はかかりませんが、属性データの整備が必要です。
属性データとは、管理したい文書を表す属性をデータ化したものとなります。
電子文書を単純にシステムにアップするだけではなく、その文書の属性であるタイトルや責任部署、作成日付、保存期限などをデータ化してシステムに投入することで初めて、高度な検索やデータ一覧での並べ替え、フォルダ構造を組み替えての閲覧が可能となります。
然しながら、これら属性データを作成するには人手というコストがかかることになります。
共有フォルダと文書管理システムの棲み分け
デメリットのところで述べてきたように、文書管理システムの導入や運用にはコストがかかりますし、導入後のデータ作りにも同様にコストがかかります。そのため、全ての保管文書を文書管理システムに投入するのではなく、選別された文書を投入することになります。
共有フォルダと文書管理システムのその棲み分けルールを決定し周知することが必須になります。
その棲み分けの例を以下に示します。

例:重要文書・正式文書の保管を正確に行う
文書管理システムには、承認を経て決定した正式文書や法律で保存年限がが決められいる文書を格納して保管します。
一方、それ以外の文書は共有フォルダに格納します。共有フォルダには、検討に至るまでの文書でしばらく取っておくことが必要なもの、通知文書など内部の文書など格納されることになります。

例:ワークフローでの運用が必要な文書や検索性が求められる文書の活用に使用する
文書のほとんどは共有フォルダに格納することで運用し、文書管理システムには高度な検索性や承認の足跡を辿ることが必要な文書に限定して格納します。例えば、契約書や稟議書が該当します。
文書管理システムも共有フォルダもいいものを導入しただけではその効果は得られません。上手に棲み分けて運用しましょう。
文書管理システムに備わっている高度な検索機能やワークフロー機能などはとても魅力的ですが、運用にあたってはデータづくりなどの準備を要します。
組織内で使用目的を明らかにして、導入やデータづくりをすることをお勧めします。
文書管理コンサルティング/石川
※関連記事
組織の知カラとは?
文書管理の専門家が長年培ってきたノウハウを企業担当者に向けて配信するサイトです。
文書の業務効率化リスク低減を目指す
7つの文書管理支援メニュー

文書管理の悩みを実践的な手法で解決するメニューを紹介しています。文書管理でどうしたらいいかわからない時はまずこちらを見てみましょう。
【必読】
文書管理ルールのまるわかりガイドブック

もし文書管理ルールを見直すのであれば、是非この資料を見てみましょう。文書管理の必要性、課題、解決策などにについて解説した資料となっています。

文書管理サービスページから6つの資料がダウンロードできます。
このページでは以下の説明と資料のご案内をしています。
文書管理ルール
ファイルサーバー共有フォルダ
ペーパーレス化支援
法定保存文書
文書管理研修サービス
維持管理支援
記事カテゴリ一覧
会社情報
© Nichimy Corporation All Rights Reserved.


